

森銀器製作所
古くから銀器製造が盛んだった東京・下谷区(現在の台東区)に生まれた初代、森善之助氏が、銀座の名工・田島勝之氏に弟子入りし、昭和2年(1927年)、鍛金師として独立。カトラリーやメダル、装飾品など、銀製品を幅広く製作する銀の総合メーカーに発展した。現在は善之助氏の五男、將氏が、五代目の社長を務めている。キャッチフレーズは“銀の爪楊枝から、金のお風呂まで”。銀の爪楊枝は現在も人気商品で、22金のお風呂は東京オリンピックの年に実際に注文が入って製作したという。

- 「東京手仕事」コーナーで実演中の韮澤さん。銀ののべ板を鉄床(かなとこ)に当て、細かく金槌で打つ作業によって、平らな銀が美しい曲面を描きながら立ち上がり、ぐい呑みへと変化していきます。元ののべ板の大きさと厚さから、どんな大きさの器を作るかは、韮澤さんの叩き方次第。叩く強さによって仕上げの厚さを加減し、叩く場所によって形を整えます。


- 途中で材料を足したり、取り除いたりすることができない鍛金作業。叩く強さや場所によって、仕上げの厚さを0.1mm単位で調整し、形を整え、さらには鎚の跡が表面の飾りにもなります。1回金鎚を振り下ろすことで三つのことを同時に進め、しかも後戻りができない作業ですが、叩く速度は「1秒で2~3回くらい」と韮澤さんはこともなげに言います。ひとつのぐい呑みを作る所要時間は、約2時間。2万回あまり叩く計算になります。


- 鍛金に使う道具は、金鎚と、木の土台に打ち付けた鉄床です。金鎚は、柄の長さと鎚のバランスなどを自分に合ったものにするため、木の柄と鎚の部分を別々に購入し、韮澤さん自身で組み合わせて作ったそう。鉄床は、頭の部分の微妙なカーブや角を使って、底の角を出したり、曲面のアールを出したりするそう。これだけの道具で、一見“餃子の皮”のように見えるのべ板が、輝く酒器となるのです。


- この仕組みを受け継いだ「ながれ」のデザインのいちばんの特徴であるストライプ状の鎚目は、真上から見ると均等な幅のストライプですが、角度によって幅が変わって見え、まるで川の水の流れのような動きが出ます。「平面図ではただ真っ直ぐに線を引いただけですが、曲面にこのラインをスジ打ちするのは、作る側からすると厄介な作業。中心から放射線状に打つのとは違い、何も目安がないところに打っていくので、幅を測って、下書きをしながら進めます。」と韮澤さん。


- 高台が別になっているのも、デザインの特徴です。杯を傾け、高台に戻すという、食卓での新しいしぐさが生まれます。使わないときは、インテリアのアクセントとして飾っても素敵。さらに、森社長が提唱する“マイ猪口”にも便利です。これは、ジャケットの胸ポケットにいつも自分の杯を忍ばせておき、宴会の場でお酌を受ける際にやおら取り出す、という楽しい習慣。「ながれ」は高台がない分、ポケットに入れてもスマートに持ち歩けそうです。


- 「将来は、この高台部分に江戸切子などのガラスや焼き物、塗り物など、ほかの伝統工芸との組み合わせも出来るのではないかと考えています。」と森社長。森社長のアイデアにより、漆の塗師とのコラボレーションはすでに始まっていて、外側は蒔絵がほどこされた漆器、内側が銀のタンブラーも製作されています。
トントンと小気味よい鎚音とともに、1枚の平らな銀ののべ板が立体的な器へと少しずつ形を変えていきます。鍛金は、金属を鎚で鍛えて形を作る技術。昭和2年(1927年)創業の森銀器製作所は、現在も7名の職人(内2名が国指定伝統工芸士)を擁して銀製品を作り続けている、銀製品の総合メーカーです。アイデアマンの森 將(もり まさる)社長と伝統工芸士の韮澤竜興(にらさわ たつおき/号:龍興)さんにお話を伺います。
江戸時代から続く「東京銀器」の担い手として。

江戸時代に貨幣を鋳造・検印する組織「金座・銀座」が設立し、全国各地の大名屋敷が軒を連ねた江戸。ここで、鍛金などの技術を用いて器ものを作る銀師(しろがねし)、それに飾りをほどこす彫金師、お神輿の飾り金具などを作る飾師などの職人文化が花開きました。東京の伝統工芸の魅力を国内外に発信する「東京手仕事」プロジェクトに、伝統工芸認定「東京銀器」として参加している森銀器製作所。実演を行っている、日本橋三越本店5階「東京手仕事」コーナーを訪ねます。
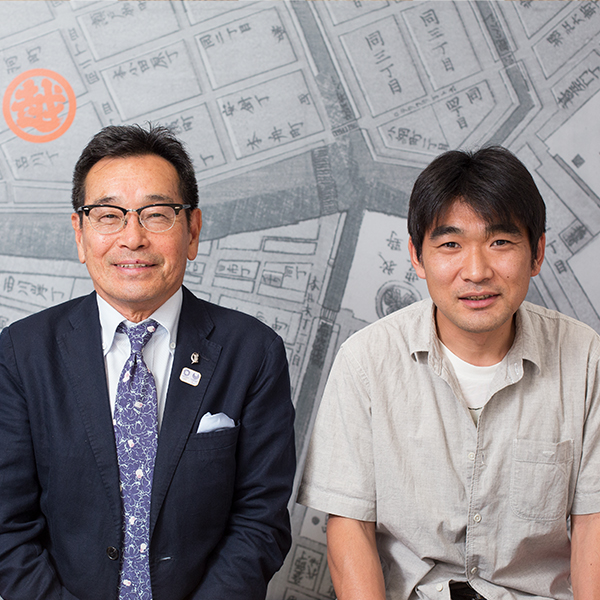




鍛金の伝統工芸士としてさまざまな作品を送り出している韮澤さんは「中学生の頃から人と話をするのが苦手で、将来サラリーマンになって営業をしたりすることは考えられなかった。」そう。そのため、東京都立工芸高校に進学し、金属工芸科(当時)で鍛金、鋳物、彫金などを学んだといいます。その後、森銀器製作所で研鑽を積み、伝統工芸士の指定を受けました。伏せると富士山の美しい稜線が現れるぐい呑みなど、現代の暮らしに潤いを与えてくれるさまざまな作品を生み出しています。

「東京手仕事」で、新たなデザインに挑戦。
森銀器製作所は、江戸時代から続く東京の伝統工芸を国内外に発信する「東京手仕事」プロジェクトに参加しています。「東京オリンピックに向けて、国内だけでなく、海外からも大勢の人が東京に集まります。色々な場面で東京の伝統工芸を見ていただき、お土産として買って帰っていただきたい。そこから口コミで、その魅力が世界中に広く伝わればいいなと思っています。」と森社長。「長く銀器を作り続けてきた私たちの固定観念を、デザイナーさんとコラボレーションすることで打ち破って、新しいものづくりをしたいと考えました。」と意気込みを語ってくださいました。

この「玉盃 ながれ」は、森銀器製作所で開発した「玉盃」をもとに、デザイナーが新たにデザインしたもの。「玉盃」とは、中にお酒を入れると、光の屈折によって杯の縁が底に映り込み、「玉(ぎょく)」が立体的に浮かび上がるように見えるぐい呑みのこと。森銀器のオリジナルです。杯に満たしたお酒の中に、満月、あるいは龍が手にしている玉のような球体が見え、飲み干すと消えてしまう不思議な杯。底を鏡のように磨くことで縁を映り込ませ、玉が現れる仕組みです。


このストライプは「ある程度平行できれいに見えるように打ちますが、きれい過ぎると逆に手作りに見えなくなってしまう。さらに、深く彫り過ぎるとくどくなるし、浅く彫るとあっさりし過ぎてしまう。そうした塩梅は、自分の感覚でしかないので、気を遣いますね。」韮澤さんの、作り手ならではの感想です。一見シンプルなデザインですが、デザイナーとコラボレーションしたからこそ生まれた作品に仕上がりました。左の細かなツヤ消しの面は“梨”の表面に似ていることから鍛金業界では「梨地」と呼ばれています。「デザイナーさんは、これを“マット仕上げ”と呼んでいました。そんなところも新鮮で面白かったです。」と韮澤さん。右のツヤのある仕上げは、職人さんの間では“テカ”などと呼ばれているそうですが、デザイナーさんは“ミラー仕上げ”と呼んでいたそう。



こうした取り組みを行うのも、銀製品をハレの場だけでなく、日常使いして欲しいという思いから。「銀は、使わずにしまっておくと黒く酸化・硫化しますが、使っていれば、黒くなるヒマはありません。銀のもつ温かみや、本物の輝きを味わいながら毎日のお酒を飲むことは、日々の暮らしにどれほどの潤いをもたらしてくれることか。少しずつ素材感が変化したり、小さな傷がついたりすることで、銀製品は、単なるモノではなく、使う人の歴史が積み重なったかけがえのないものになるのです。」と熱く語り、その後、“マイ猪口”を胸に夜の街へと消えた森社長。楽しいお話をありがとうございました。
<森銀器製作所>の商品を購入
検索に該当の商品がありませんでした。
関連記事











